| ご依頼専用ダイヤル | 0120-604-405 | |
| お問い合わせ(東京本部) | 03-6868-6040 | |
| お問い合わせ(福岡校) | 093-592-6658 | |
お問い合わせメール |
||
| ws-spaceone |
普連土学園中学校受験指導はスペースONEのプロ家庭教師にお任せください。
| ご依頼専用ダイヤル | 0120-604-405 | |
| お問い合わせ(東京本部) | 03-6868-6040 | |
| お問い合わせ(福岡校) | 093-592-6658 | |
お問い合わせメール |
||
| ws-spaceone |
普連土学園中学校高等学校算数過去問研究
2009年度普連土学園中学校第1回算数入試問題は 1.計算3問,2.小問2問(平面図形の求積,速さの平均) 3.通過算とグラフ 4.立体図形 の構成で、例年通り 3・4は2人の会話で解法をリードする設問形式でした。今回は 3 通過算とグラフを T先生とS子さんの質疑応答形式を解説します。
算数入試問題(通過算にチャレンジ)
| 3 次の文はT 先生とS 子さんの会話です.空欄に適するものを入れなさい.⑨, ⑪については適語を丸で囲みなさい.解答欄に「式」とある場合には,式や考え方も書きなさい. S 子: 先生,今年の1 次試験はどんな問題ですか. T 先生: 次のような,関数のグラフの問題を考えてみましょう.図1 のような山あいの渓谷を鉄道の線路がまっすぐに通っています. 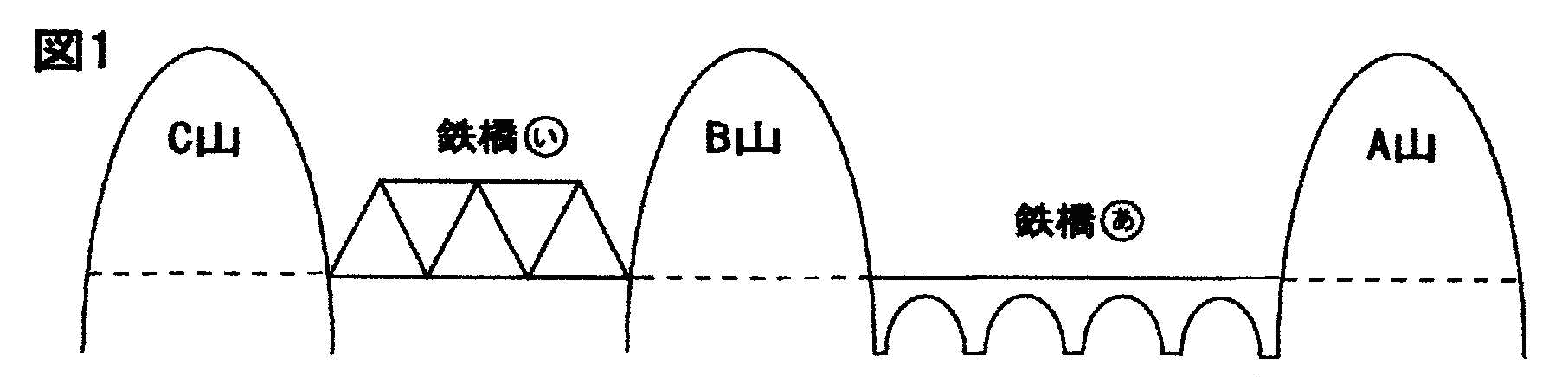 ある旅客列車が一定の速さで,「A 山トンネルを抜け,鉄橋(あ)を渡り,B 山トンネルをぬ抜け,鉄橋(い)を渡り,C 山トンネルに入る」というように図1 の右から左に向かって通り抜ける様子を観察しました.このときの列車の見えている部分の長さを縦軸,時間を横軸として関係を表したものが,図2 のグラフです.列車の先頭がA 山トンネルを出てきたときから時間を計っているので注意してね. 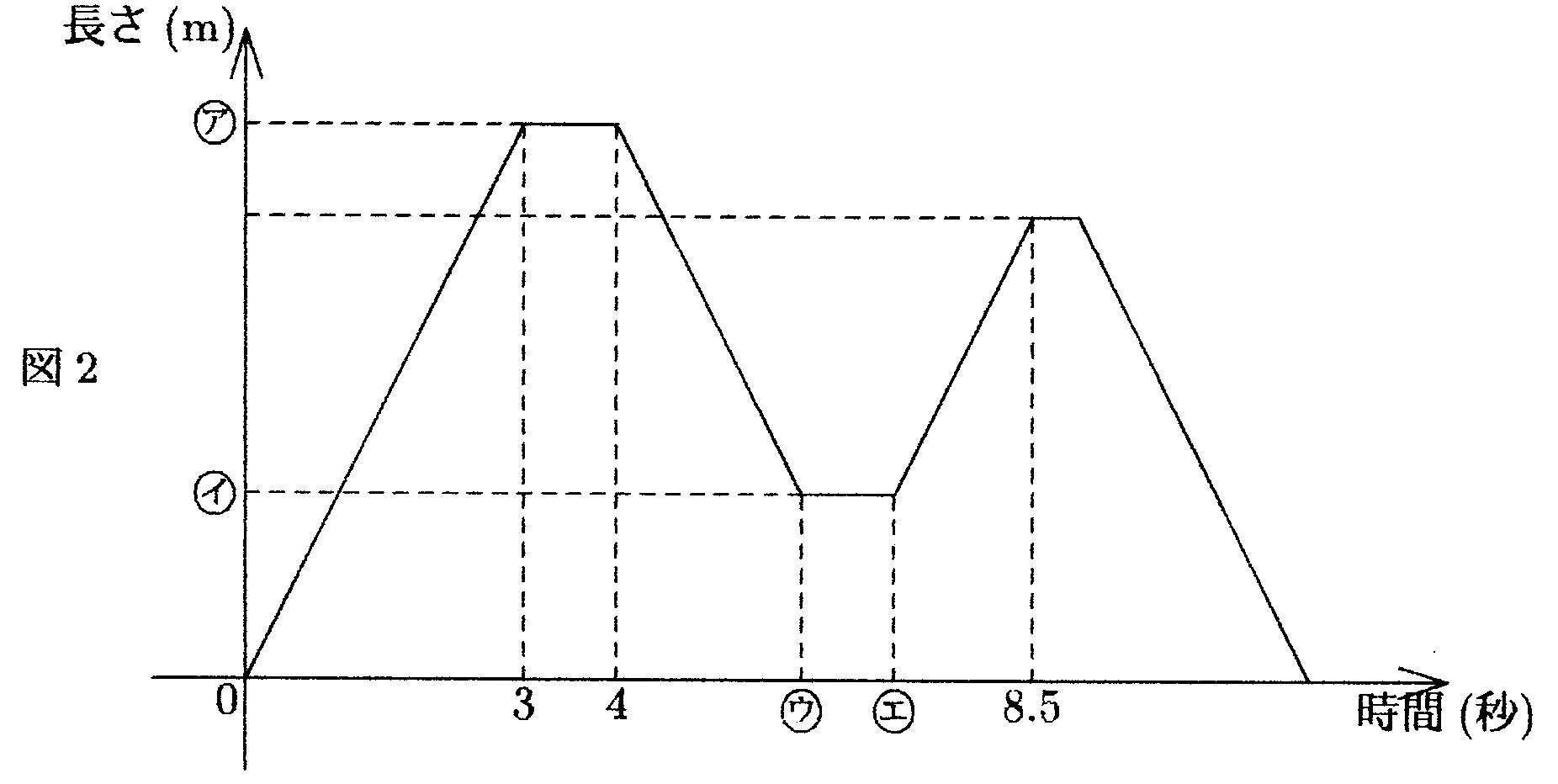 S 子: そっか,列車は鉄橋を通過している部分しか見えないんですね。グラフを見てみるとA 山トンネルから出てきた列車は,だんだん見える部分が増えていき,3 秒後から4 秒後の間は鉄橋(あ)上で列車全体が見えていたことがわかりますね. T 先生: そういうことよ.列車が時速72km だとして考えてみましょう. S 子: ということは,列車は秒速① mだから(ァ)の目盛,つまり,列車の長さは② m で,鉄橋(あ)の長さは③ m ということになりますね. T 先生: その通り.さらに,B 山トンネルの長さは40m だったことがわかっているのよ. S 子: ということは,(ィ)の目盛は④ で,(ゥ)の目盛は⑤ で,(ェ)の目盛は⑥ になりますね. T 先生: 列車の先頭が鉄橋(い)にさしかかった時間は⑦ 秒後で,C 山トンネルに入る時間は⑧ 秒後だから,鉄橋(い)の長さが求められるでしょう. S 子: そうか.グラフの2 度目の平らな部分は,列車の先頭が鉄橋(い)を渡りはじめてから最後尾がB 山トンネルに入るまでを表していますね.3 度目の平らな部分は,列車の⑨(先頭最後尾)が⑩ から⑪(先頭最後尾)が⑫ までを表すんですものね.このことと,鉄橋(い)の長さが列車の長さより短いことに注意すれば,鉄橋(い)の長さは⑬ m ということになります. T 先生: そうね.今度は,観察者から先頭と最後尾の両方が見えていた時間の合計を求めてみて. S 子: ⑭ 秒後から⑮ 秒後の⑯ 秒間と, ⑰ 秒後から⑱ 秒後の⑲ 秒間だから,全部で⑳ 秒間です. T 先生: よくできたわね.では最後の問題よ.旅客列車と同じように図1で右から左へ時速72km で通り抜けていく,長さ150m の貨物列車があります.列車の見える部分の長さと時間の関係を表したグラフを解答欄(21)に描き込んでみて. S 子: 列車の先頭がA 山トンネルを出てきたときから描き始めるんですね. (描き終えて) これで,いいですか. T 先生: よくできました. |
||||
スペースONEのプロ家庭教師の解答で、普連土学園中学校の発表ではありません。
|
|
|
|
| 普連土学園中学校・高等学校合格のための受験情報に戻る |
| 普連土学園中学校・高等学校合格のための過去問対策に戻る |
| 中学受験Eラーニング(過去問研究)TOPに戻る |
| プロ家庭教師集団スペースONEリンク集 |
| 高校受験数学・英語過去問研究 |
| 大学受験過去問研究 |
| 医学部受験過去問研究 |
| 医科大学・医学部入試情報 |
このホームページのすべての文章の文責および著作権はプロ家庭教師集団スペース ONEに属します。