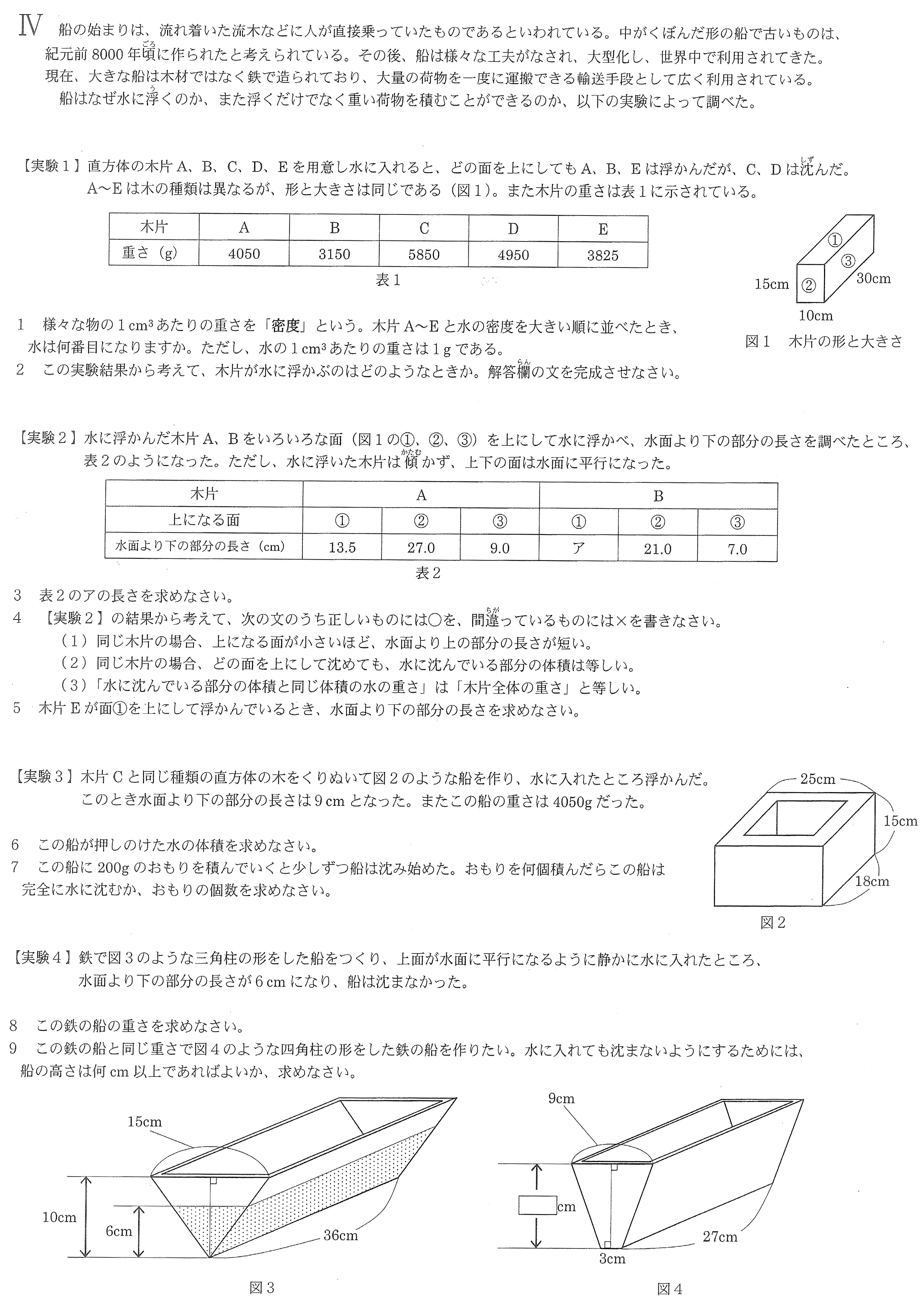中学受験指導専門プロ家庭教師の女子学院中学校過去問研究
女子学院中学校受験指導はスペースONEのプロ家庭教師にお任せください。
 |
ご依頼専用ダイヤル |
0120-604-405 |
| お問い合わせ |
03-6868-6040 |
 |
お問い合わせメール
|
|
 |
ws-spaceone |
|
 プロ家庭教師集団スペースONE
プロ家庭教師集団スペースONE
中学受験案内HOME
2015年度女子学院中学校入試問題(過去問)解答解説
女子学院中学校算数過去問研究
2015年度女子学院中学校理科入試問題は 例年通り大問4題構成で、生物・地学・化学・物理分野からの出題でした。
今回は4.浮力を解説します。浮力に関する基礎知識が無くても誘導に従って解く出題でした。
理科入試問題 4. 浮力にチャレンジ
問題4
スペースONEプロ家庭教師の解答で、女子学院中学校の発表ではありません。
1.解説解答
| 1.木片A~Eと水の密度を大きい順に並べたとき、水は何番目になりますか。ただし、水のcm3あたりの重さは1gです。 |
| 解説 |
| 木片の体積は 10×30×15 = 4500cm3 |
| 木片A,B,C,D,Eの1cm3当たりの重さは次の通り |
| A: 4500÷4500 = 0.54 ・・・⑤ |
| B: 3150÷4500 = 0.7 ・・・④ |
| C: 5850÷4500 = 1.3 ・・・① |
| D: 4950÷4500 = 1.1 ・・・② |
| E: 3825÷4500 = 0.85 ・・・③ |
| 水の1cm3あたりの重さは1gなので、DとEの間 3番目 |
|
| 別解 |
木片A~Eの体積はすべて4500㎝3なので、木片の重さによって密度の大小関係が決まる。
水のcm3あたりの重さは1gなので、体積が4500㎝3のとき水の重さは4500g になる。
このことから、大小関係はC(5850g)>D(4950g)>水(4500g)>A(4500g)>E(3825g)>B(3150g)
したがって 水は3番目になる。 |
|
| 答 3 |
|
|
2.解説解答
| 2. この実験結果から考えて、木片が水の浮かぶのはどのようなときか。解答欄の文を完成させなさい。 |
| 解説 |
| みずに浮かんだA,B,Eの密度はA=0.54,B=0.7,E = 0.85。沈んだC,Dの密度はC = 1.3,D = 1.1より水の密度1.1より密度が大きいときに木片は沈み、密度が小さいときに木片が浮かぶことがわかる。 |
|
| 答 木片の密度が水の密度より小さいとき |
|
|
3.解説解答
| 3. 表2のアの長さを求めなさい。 |
| 解説 |
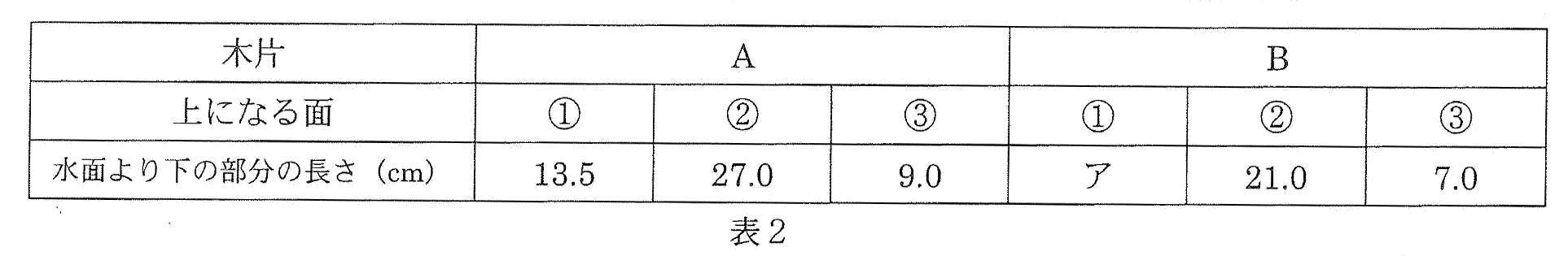 |
| 木片Bの重さは3150g,①の面積は 10×30 = 300cm2, ②の面積は 10×15 = 150cm2, ③の面積は 15×30 = 450cm2 |
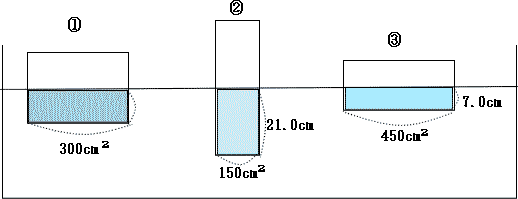 |
| 水面より下の部分の体積は ②の場合 150×210 = 31500cm3, ③の場合 450×7 = 31500cm3 |
| ②③の場合と同様 ①の場合も水面より下の部分の体積は、木片の重さと同じ体積31500cm3なので、 |
| 31500÷300 = 10.5cm |
|
| 別解1 |
Aの比重が0.9、Bの比重が0.7なので、Aの高さのうちの90%が、Bの高さのうち70%が水面下に沈むので
15×0.7=10.5㎝
|
|
| 別解2 |
| Aの②とBの②を比べると21/27=7/9倍、Aの③とBの③を比べても7/9倍になっていることから、13.5×7/9=10.5㎝ |
|
| 答 10.5cm |
|
|
4.解説解答
4. 【実験2】の結果から考えて、次の文の内正しいものには○を、間違っているものには×を書きなさい。
(1) 同じ木片の場合、上になる面が小さいほど、水面より上の部分の長さが短い。
(2) 同じ木片の場合、どの面を上にして沈めても、水に沈んでいる部分の体積は等しい。
(3) 「水に沈んでいる部分の体積の水の重さ」は、「木片全体の重さ」と等しい。 |
|
| 解説 |
|
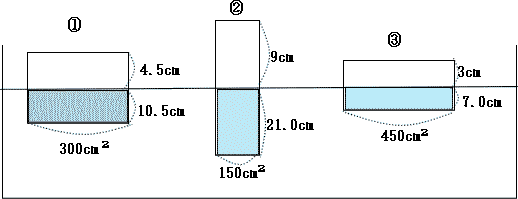 |
|
| (1) 図の通り 水面より上の部分の長さは①:4.5cm,②9cm,③3cm したがって × |
|
| (2) 水に沈んでいる部分の体積は全て3150cm3 よって ○ |
|
| (3) (2)の結果より○ |
|
4 (1) 木片Aの場合で計算してみましょう。
上になる面が①の場合
(①の面積)=10×30=300㎝^2、(水面より上の部分の長さ)=15-13.5=1.5㎝
上になる面が②の場合
(②の面積)=15×10=150㎝^2、(水面より上の部分の長さ)=30-27=3.0㎝
上になる面が③の場合
(③の面積)=30×15=450㎝^2、(水面より上の部分の長さ)=10-9=1.0㎝
以上の結果から、上になる面が小さいほど、水面より上の部分の長さは短くなりますので×ですね。
(2) これも木片Aの場合で計算してみましょう。
上になる面が①の場合
(水に沈んでいる部分の体積)=13.5×10×30=4050㎝^3
上になる面が②の場合
(水に沈んでいる部分の体積)=27×15×10=4050㎝^3
上になる面が③の場合
(水に沈んでいる部分の体積)=9.0×15×30=4050㎝^3
以上の結果から○であることが分かります。
(3) (2)の計算結果を見ると、水に沈んでいる部分の体積はすべて4050㎝^3で、これは木片の重さと値が同じなので○ですね。実験2の結果から以下のことがいえます。
「浮力の大きさは物体が押しのけた水の重さに等しい。」
これはとても大事なことなので覚えておきましょう。
答 (1)× (2)○ (3)○
|
|
| 答 (1)×(2)○(3)○ |
|
|
|
5.解説解答
| 5.木片Eが面①を上にして浮かんでいるとき、水面より下の部分の長さを求めなさい。 |
| 解説 |
| 木片Eの重さは3825gなので、水に沈む部分の体積は3825cm3。 |
| ①の面積は10×30 = 300cm2。 |
| 水面より下の部分の長さは 3825÷300 = 12.75 |
5 4 (3)が○であることが使えます。木片Eの面①を上にして浮かべ、水面より下の部分の長さを□㎝とおくと、
□×10×30=3825㎝^3ですから、□=12.75㎝と求まります。
答 12.75㎝ |
| 答 12.75cm |
|
|
6.解説解答
| 6. この船が押しのけた水の体積を求めなさい。 |
| 解説 |
| 「水に沈んでいる部分の体積の水の重さ」は、「船全体の重さ」と等しいので、船の重さ4050gがこの船が押しのけた水の体積4050cm3。 |
6 船の底の面積は、18×25㎝^2なので、押しのけた水の体積は18×25×9=4050㎝^3です。
答 4050㎝^3
|
| 答 4050cm3 |
|
|
7.解説解答
| 7. この船に200gのおもりを積んでいくと少しずつ船は沈み始めた、おもりを何個積んだらこの船は完全に水に沈むか、おもりの個数を求めなさい。 |
|
| 解説 |
|
水面より上に出ている船の体積は 25×18×(15 - 9) = 2700cm3
よって 2700g以上のおもりを積めばよいので
2700÷200 = 13.5
したがって おもりの数は14個 |
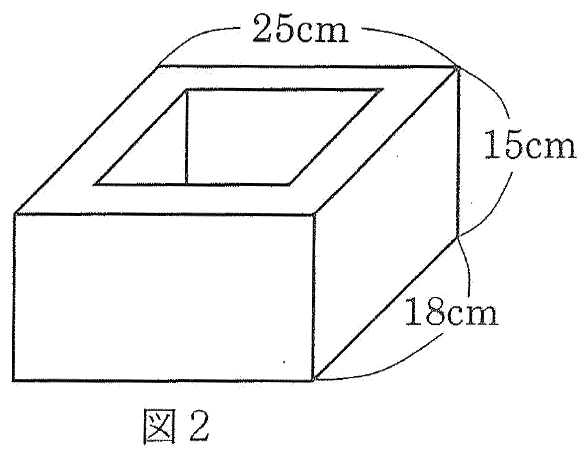 |
| 7 船の上面が水面と一致したとき、水面の下の長さが15㎝になります。浮力の大きさは物体が押しのけた水の重さに等しいから、「水面下の体積=船の重さ+おもりの重さ」の関係が成り立ちますね。船に積まれているおもりの数を□個とおくと、15×28×18=4050+200×□より、□=13.5と求まりますが、□は個数なので、整数でなければなりません。この結果より13個だと船はまだ完全に沈みませんが、14個であれば船は完全に沈むことがわかります。答 14個 |
|
| 答 14個 |
|
|
|
8. 解説解答
| 8. この鉄の船の重さを求めなさい。 |
|
| 解説 |
|
水面より下の部分は 相似比より三角形の面積を底面積、高さを36cmとすると
10:6 = 5:3 より
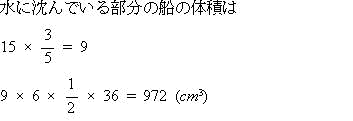
したがって、この鉄の船の重さは 972g |
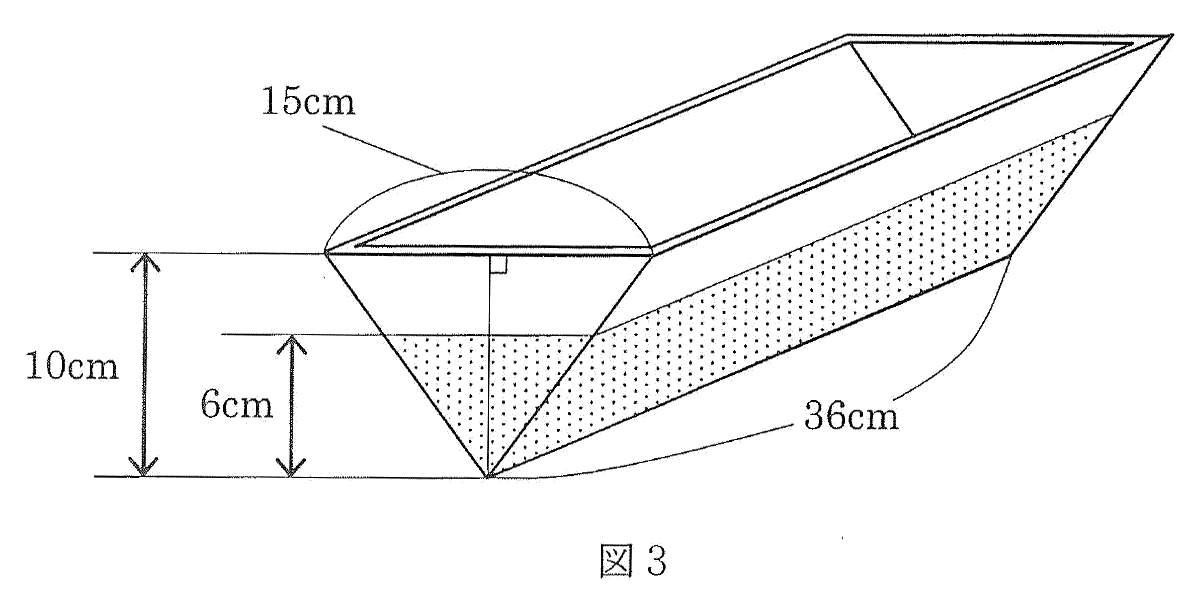 |
8 船は沈まなかったので、「浮力の大きさは物体が押しのけた水の重さに等しい。」が成り立ちます。
まず、この鉄の船が押しのけた水の体積を求めましょう。底面の三角形の底辺の長さを□㎝とすると、
10:6=15:□より、□=9㎝になります。よって求める体積は9×6÷2×36=972㎝^3
水1㎝^3あたりの重さは1gなので、求める重さは972×1=972gになります。
答 972g |
|
| 答 972g |
|
|
|
9. 解説解答
| 9. この鉄の船と同じ重さで図4のような四角柱の形をした鉄の船を作りたい。水に入れても沈まないようにするためには、船の高さは何cm以上であればよいか。求めなさい。 |
| 解説 |
|
水面下の体積が972cm3になるときの高さは
(9 + 3)×□÷2×27 = 972
□ = 972÷27×6)
□ = 6
したがって 6cmの深さまで船は沈むので、沈まないようにするためには6cm以上であればよい。 |
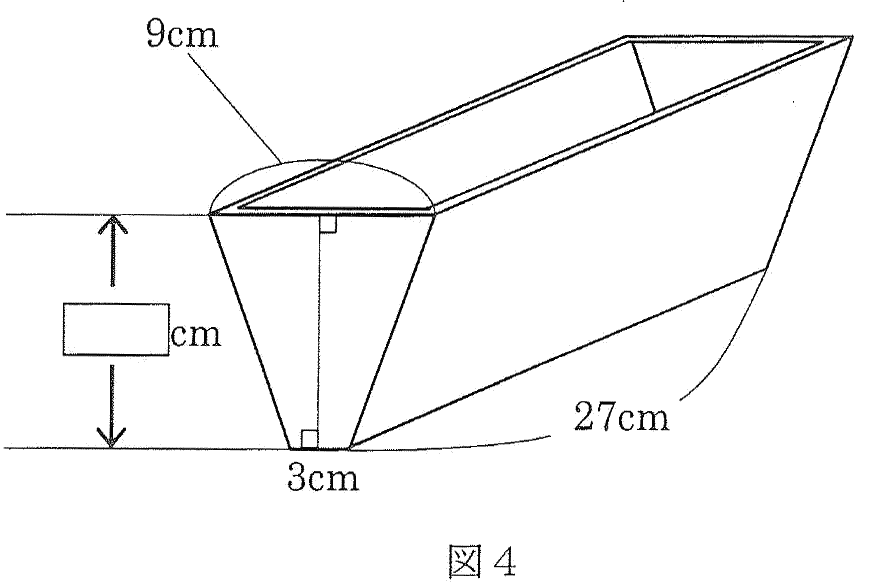 |
9 船がギリギリ沈まないとき、押しのけた水の体積は(9+3)×□÷2×27=162×□㎝^3になり、
これが船の重さ972gに等しいので、162×□=972より□=6㎝と求まります。
よって、船の高さを6㎝以上にすれば水に入れても船は沈みません。
答 6㎝以上であればよい |
|
| 答 6cm |
|
|
|
HOME
このホームページのすべての文章の文責および著作権はプロ家庭教師集団スペース ONEに属します。